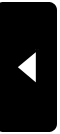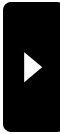2008年02月14日
区切りがあいまいな社会ー3 身についた芸
プロの歌手が経営する民謡酒場に行ったことがある。自ら三線を弾きながら歌う。でも何かプロ意識のはき違えがあるような気がした。
「私が歌っている時は、お客様は静かにして下さい」、と強制されているような感じ。
出番が終わってカラオケに切り替わった。座持ちの良いホステスが客を乗せながら歌い始めた。笑いをとり、しかもさきほどのプロより上手。陽気なオーラが漂っているような振る舞いに感心した。沖縄では唄三線というが、音楽全体が身体に染み付いている。
新しいボトルを頼んだ。別の女性が軽快な音楽に合わせて踊りながら運んできた。両手にボトルを捧げ、右に左に振りながら。おそらくは子供の頃から自然に身についた体の動きだろう。一瞬のしぐさに沖縄伝統の芸がしみこんでいる。
すごい!
沖縄では厳しく芸を磨く、という修業が成り立たない。お客様に合わせて楽しくパフォーマンス出来る方が評価される。でもその方がもともとの芸能の精神ではなかろうか。
「私が歌っている時は、お客様は静かにして下さい」、と強制されているような感じ。
出番が終わってカラオケに切り替わった。座持ちの良いホステスが客を乗せながら歌い始めた。笑いをとり、しかもさきほどのプロより上手。陽気なオーラが漂っているような振る舞いに感心した。沖縄では唄三線というが、音楽全体が身体に染み付いている。
新しいボトルを頼んだ。別の女性が軽快な音楽に合わせて踊りながら運んできた。両手にボトルを捧げ、右に左に振りながら。おそらくは子供の頃から自然に身についた体の動きだろう。一瞬のしぐさに沖縄伝統の芸がしみこんでいる。
すごい!
沖縄では厳しく芸を磨く、という修業が成り立たない。お客様に合わせて楽しくパフォーマンス出来る方が評価される。でもその方がもともとの芸能の精神ではなかろうか。
Posted by おさむちゃん at
10:12
│Comments(0)
2008年02月12日
区切りがあいまいな社会ー2 プロはどちら?
本土の飲み会ならばどうだろう。特に会社の場合は時間は予定どおり、中味盛り沢山のように感じる。組織の規律・時間厳守の習慣が影響しているようだ。
例をあげよう。夕方7時開始。全員の到着を待って乾杯。そのうち一気飲み、近況報告、一芸披露などのメニューをこなす。時間が迫ると締めの言葉、三三七拍子などがあって解散。
もっとも抜ける時は自由という習慣も根付いているようだ。終わりよければ全て良し、の反対で最初の形が整えばあとのグズグズはしょうがない、というルールだろう。
沖縄のセレモニーは「かぎやで風」という踊りで始まることが多い。会場がざわついていようが静かだろうが関係なく、ゆったりとスタートする。誰かが鑑賞している訳ではない。
本土の沖縄酒場に行って感じる違和感は、このへんにある。踊りが始まれば、客も酒を飲んでいるのは失礼と感じるのだろうか。グラスと箸を置き、舞台に注目する。演者も客の視線を意識しながら緊張して踊る。 その間、宴席のなごやかなムードは一変し、「芸能鑑賞」の時間になってしまう。
やめとけ、そういう堅苦しいのは。沖縄でも国際通り沿いの観光客向けのショーは「芸の披露」であり、最後のわざとらしいカチャーシーで全員参加を促して終わる。
一方、外れの民謡酒場での地元向けのショーは、聞いている人もいれば飲んでいる人もいる。誰もが、その場に居合わせているだけ。
舞台と客席との境もない。みんな芸達者だからどちらがプロか分からないこともある。
例をあげよう。夕方7時開始。全員の到着を待って乾杯。そのうち一気飲み、近況報告、一芸披露などのメニューをこなす。時間が迫ると締めの言葉、三三七拍子などがあって解散。
もっとも抜ける時は自由という習慣も根付いているようだ。終わりよければ全て良し、の反対で最初の形が整えばあとのグズグズはしょうがない、というルールだろう。
沖縄のセレモニーは「かぎやで風」という踊りで始まることが多い。会場がざわついていようが静かだろうが関係なく、ゆったりとスタートする。誰かが鑑賞している訳ではない。
本土の沖縄酒場に行って感じる違和感は、このへんにある。踊りが始まれば、客も酒を飲んでいるのは失礼と感じるのだろうか。グラスと箸を置き、舞台に注目する。演者も客の視線を意識しながら緊張して踊る。 その間、宴席のなごやかなムードは一変し、「芸能鑑賞」の時間になってしまう。
やめとけ、そういう堅苦しいのは。沖縄でも国際通り沿いの観光客向けのショーは「芸の披露」であり、最後のわざとらしいカチャーシーで全員参加を促して終わる。
一方、外れの民謡酒場での地元向けのショーは、聞いている人もいれば飲んでいる人もいる。誰もが、その場に居合わせているだけ。
舞台と客席との境もない。みんな芸達者だからどちらがプロか分からないこともある。
Posted by おさむちゃん at
12:53
│Comments(0)
2008年02月11日
区切りがあいまいな社会ー1
シタールの演奏を聴いたことがある。舞台にはシタールが数台。演奏者とおぼしきインド人達が入ってきて、調弦が始まった。何人かはかなり熱心に調弦している。主役らしい真ん中の男も時々やっている。調弦なのか演奏しているのか分からないほど熱中している。そのうち止めてしまった。どうやら演奏会が終わったようだ。始まりも終わりもない。過ぎ去った風のような時間。どこで盛り上がったのか分からないので拍手のきっかけも不明。
沖縄の飲み会も似たようなものだ。開始はあえて言えば夕方6時から10時の随時。7時になっても8時になっても来ないからだめだと思うと現れたりする。自分が参加した時が会の始まり、と心得ているのだろう。だから人がぽつりぽつりと現れ、そのたびに新しいグラスに酒が注がれる。先に来た人がいらいらして待っていることも、後から来た人が咎められることもない。遅れた人はその時点からスタート。改めて乾杯を重ねながらゆるやかに進行してゆく。終わり近くに顔を出す人もいる。一次会をどこかで済ませた後、義理を果たすために来たのだ。
沖縄の飲み会も似たようなものだ。開始はあえて言えば夕方6時から10時の随時。7時になっても8時になっても来ないからだめだと思うと現れたりする。自分が参加した時が会の始まり、と心得ているのだろう。だから人がぽつりぽつりと現れ、そのたびに新しいグラスに酒が注がれる。先に来た人がいらいらして待っていることも、後から来た人が咎められることもない。遅れた人はその時点からスタート。改めて乾杯を重ねながらゆるやかに進行してゆく。終わり近くに顔を出す人もいる。一次会をどこかで済ませた後、義理を果たすために来たのだ。
Posted by おさむちゃん at
11:39
│Comments(0)
2008年02月10日
沖縄的経営ー7 嫌いにならないで
「好き」の裏に、「好きなら、いつでも私の味方でいて。少々悪いところがあっても見逃して」という気持ちがあるような・・。
ここで事務局長に戻る。(沖縄的経営2の後半を参照)
彼は「本当は(米軍ではなく民間で働きたかった。」とも弁解していた。手紙の真意は、「私はあなたに嫌われるような悪いことをするが、ウチナーンチュへの愛情は捨てないでほしい。」と矛盾したことを訴えている。
沖縄は戦争中は本土から捨て石にされ、戦後は基地を押し付けられている。沖縄の人は愛情に飢えているのかもしれない。
ここで事務局長に戻る。(沖縄的経営2の後半を参照)
彼は「本当は(米軍ではなく民間で働きたかった。」とも弁解していた。手紙の真意は、「私はあなたに嫌われるような悪いことをするが、ウチナーンチュへの愛情は捨てないでほしい。」と矛盾したことを訴えている。
沖縄は戦争中は本土から捨て石にされ、戦後は基地を押し付けられている。沖縄の人は愛情に飢えているのかもしれない。
Posted by おさむちゃん at
12:01
│Comments(0)
2008年02月08日
沖縄的経営ー6 私のこと好き?
それに、沖縄に一度住んだら帰ってはいけないのか。例えば「移住」という言葉。本土の中ならどこでも「引越し」で済む。仲村清司という作家と酒を飲んでいる時に話題になった。彼は大阪から引っ越してきた。が人は移住と呼ぶ。
そうだ。何故、沖縄だけが移住なのだ?大学を定年で辞めたらどうするのか、と聞かれることがある。沖縄にいよう、と思っているんですよ、と答える。猫にまたたび、ウチナーンチュに移住。「やはり沖縄が好きなんですねえ」とゴロゴロ喉を鳴らし、膝に上ってくる。-違うんです、ちょっと。
「沖縄が好き」と聞く時に、こんな心情はないだろうか。「わたし昔と比べて容貌は落ちたわ。ええどうせそうよ。皺も増え、たるみも目立つ。でも、でも色気だけはまだまだ負けないつもりよ。だからみんなお店に来るんでしょ。私を好きなんでしょ。」-違います。
ママの店は料理もうまいし、値段も安い、雰囲気も良い。だから通っているのであって色気が目当てなら他の店いくらでもおまっせ。好きや嫌いや、いちいち訊かんといて。
もうちょっと自信持たんかい。喜多見じゃママの所が一番たい。(済みません、突然、東京の世田谷の外れの地名が出てきて)
そうだ。何故、沖縄だけが移住なのだ?大学を定年で辞めたらどうするのか、と聞かれることがある。沖縄にいよう、と思っているんですよ、と答える。猫にまたたび、ウチナーンチュに移住。「やはり沖縄が好きなんですねえ」とゴロゴロ喉を鳴らし、膝に上ってくる。-違うんです、ちょっと。
「沖縄が好き」と聞く時に、こんな心情はないだろうか。「わたし昔と比べて容貌は落ちたわ。ええどうせそうよ。皺も増え、たるみも目立つ。でも、でも色気だけはまだまだ負けないつもりよ。だからみんなお店に来るんでしょ。私を好きなんでしょ。」-違います。
ママの店は料理もうまいし、値段も安い、雰囲気も良い。だから通っているのであって色気が目当てなら他の店いくらでもおまっせ。好きや嫌いや、いちいち訊かんといて。
もうちょっと自信持たんかい。喜多見じゃママの所が一番たい。(済みません、突然、東京の世田谷の外れの地名が出てきて)
Posted by おさむちゃん at
12:03
│Comments(0)
2008年02月07日
沖縄的経営ー5 病気じゃないとだめ?
沖縄を何度も訪れるようになると、「あなたも沖縄病ですね」と言われる。ここまではどの地方にもよくある話だ。しかしその先に「沖縄が好きですか」という質問がくる。最初のうちこそ「ええ好きです」と無邪気に答えていたが、待てよ。どうもすんなり同意するのはまずいのではないか。バーのママがお客さんみんなに「愛してる?」と聞くようなもので節操がないのではないか。
好きでもなく嫌いでもなく沖縄に滞在しているビジネスマンや、ウチナーンチュと結婚して住んでいるヤマトンチュはどうするのだ。ちなみにこの場合、男をウチナームク(婿)、女をウチナーヨメ(嫁)と呼ぶ。
彼らは、沖縄が好きか嫌いか考えたことはないが彼、彼女と恋におちたので結果としていまここにいる、はずだ。
好きでもなく嫌いでもなく沖縄に滞在しているビジネスマンや、ウチナーンチュと結婚して住んでいるヤマトンチュはどうするのだ。ちなみにこの場合、男をウチナームク(婿)、女をウチナーヨメ(嫁)と呼ぶ。
彼らは、沖縄が好きか嫌いか考えたことはないが彼、彼女と恋におちたので結果としていまここにいる、はずだ。
Posted by おさむちゃん at
14:38
│Comments(0)
2008年02月05日
沖縄的経営 4 米軍好きの?人々
前回でまだ言い足りないことがある。それは事務局長が辞めるときの手紙だ。「これで沖縄の人を嫌いにならないで下さい」とあった。いま突然辞めたら予備校に迷惑がかかる。分かってはいるが自分は米軍に行く。何故なら基地内の仕事は給料が高く、休みも多く、安定しているから、とは書いてなかった。
沖縄の人の就職希望は一に公務員、二に米軍基地、三四がなくて五にスーパー、テレビ局、新聞、銀行などだろうか。
海兵隊の求人募集には常に2万人が応募、とも聞いた。テレビには基地で働くための英語予備校のCMが流れている。本土から来た人が「これでは基地返還は無理」と感じるのも分かる。
沖縄の人の就職希望は一に公務員、二に米軍基地、三四がなくて五にスーパー、テレビ局、新聞、銀行などだろうか。
海兵隊の求人募集には常に2万人が応募、とも聞いた。テレビには基地で働くための英語予備校のCMが流れている。本土から来た人が「これでは基地返還は無理」と感じるのも分かる。
Posted by おさむちゃん at
12:24
│Comments(0)
2008年02月04日
沖縄的経営―3 恩義に厚い?人々
右翼の車がスピーカーを鳴らしながら巡回してくる。「神聖な学校を東京の資本に売り渡すな」とのこと。バカバカしくて聞いてられない。お前たちこそ「神聖な学校」に近づくな。うるさくして学生に迷惑かけないでほしい。おそらく誰かが糸を引いている。警察に相談すると、車庫とばしの違反とかですぐに右翼の車は来なくなった。
怪しい人物から電話。今の予備校の名前は俺が使っているのと同じだ、と脅し。こちらは商標登録しているので無視した。
こうした「楽しい」出来事が続いた末、予備校閉鎖か譲渡に決めた。学生数は多くはないが、途切れることもない。2000万円の収入だから少数で堅実にやっていれば経営は成り立つ。先生方に200万円で差し上げた。別の場所で開校するというので花を贈った。お祝いにも行った。その後彼らからは何の連絡も無い。
沖縄で経営者をやると異文化を一挙に体験できる。海外ビジネスを志す人は、とりあえずここでやって見るとよい。外国との付き合いのレッスン・ワンは沖縄から。
怪しい人物から電話。今の予備校の名前は俺が使っているのと同じだ、と脅し。こちらは商標登録しているので無視した。
こうした「楽しい」出来事が続いた末、予備校閉鎖か譲渡に決めた。学生数は多くはないが、途切れることもない。2000万円の収入だから少数で堅実にやっていれば経営は成り立つ。先生方に200万円で差し上げた。別の場所で開校するというので花を贈った。お祝いにも行った。その後彼らからは何の連絡も無い。
沖縄で経営者をやると異文化を一挙に体験できる。海外ビジネスを志す人は、とりあえずここでやって見るとよい。外国との付き合いのレッスン・ワンは沖縄から。
Posted by おさむちゃん at
16:57
│Comments(0)
2008年02月02日
沖縄的経営―2 トラブル続き
予備校は美術系だった。教室は汚い、ガラクタが多い、借りてない部屋にまでものを置いている。まったくの無秩序状態だった。いくら美術系といっても程がある。先生達は遅刻常習、時々夜中に教室で酒を飲んで奇声を発し近所まで響かせる。「時間通りに来ること、教室で酒を飲まないこと、部屋を片付けること」と言い渡した。
事務局長は月給50万円もらっていながら煙草ばかり吸って何もしない。クビにした。要になる人材を探して据えた。細かい仕事も出来るので、何ヶ月かたって常勤雇用を考えた。年に600万円を提示すると大喜びで了承してくれた。東京の理事長も承諾。しかし翌日になると要求額が620万円になった。奥さんからもっと値上げ交渉しろ、と言われたらしい。こういう人は信用できないので応じなかった。
しばらくたって不意に辞めた。米軍基地内の仕事が見つかったとのことだった。
トラブルは次々と押し寄せた。以前ここを借りていた予備校主の命を受けて、中国人留学生達が押しかけてきた。机や椅子を運び出す、という。冗談ではない、家主との約束でこちらが使うことになっている。追い返した。
事務局長は月給50万円もらっていながら煙草ばかり吸って何もしない。クビにした。要になる人材を探して据えた。細かい仕事も出来るので、何ヶ月かたって常勤雇用を考えた。年に600万円を提示すると大喜びで了承してくれた。東京の理事長も承諾。しかし翌日になると要求額が620万円になった。奥さんからもっと値上げ交渉しろ、と言われたらしい。こういう人は信用できないので応じなかった。
しばらくたって不意に辞めた。米軍基地内の仕事が見つかったとのことだった。
トラブルは次々と押し寄せた。以前ここを借りていた予備校主の命を受けて、中国人留学生達が押しかけてきた。机や椅子を運び出す、という。冗談ではない、家主との約束でこちらが使うことになっている。追い返した。
Posted by おさむちゃん at
06:16
│Comments(0)
2008年02月01日
沖縄的経営ー1
45万円の家賃を3分の1にしてくれ、と頼んだ。家主は別に嫌な顔もせず了承してくれた。月に30万円の節約。
三人の先生方には大幅な月給のカットをお願いした。22万円、20万円、18万円もらっていた人を全員一律15万円とした。これで月に7+5+3=15万円の節約。合わせて月に45万円の節約。
(30+15)×12=1年間で540万円が浮く計算だ。実行したのは8ヶ月程度だったが360万円の節約に成功した。
経費削減ばかりではなく逆に広告支出を増やし、応募者増を図った。年間2000万円の売り上げだから、めちゃくちゃな経費節減である。これは私が1年間だけ経験した素人経営者物語である。
始まりは、ある予備校から経営を任された。理事長は東京にいて忙しい。沖縄まで出張する暇がないので面倒みてくれ、とのことだった。私に経営能力があるわけではない。ただ私が沖縄にいる、大学の先生である、信用できそうだ、というだけ。
三人の先生方には大幅な月給のカットをお願いした。22万円、20万円、18万円もらっていた人を全員一律15万円とした。これで月に7+5+3=15万円の節約。合わせて月に45万円の節約。
(30+15)×12=1年間で540万円が浮く計算だ。実行したのは8ヶ月程度だったが360万円の節約に成功した。
経費削減ばかりではなく逆に広告支出を増やし、応募者増を図った。年間2000万円の売り上げだから、めちゃくちゃな経費節減である。これは私が1年間だけ経験した素人経営者物語である。
始まりは、ある予備校から経営を任された。理事長は東京にいて忙しい。沖縄まで出張する暇がないので面倒みてくれ、とのことだった。私に経営能力があるわけではない。ただ私が沖縄にいる、大学の先生である、信用できそうだ、というだけ。
Posted by おさむちゃん at
09:50
│Comments(0)
2008年01月31日
沖縄の交通法規―那覇市民の抵抗?
バスの種類・経路は不明 ―バス会社がいくつもある。遠距離には快速、高速、急行、準急があるらしく高速道路を走るのがどれか不明。市内でも回り道が続き、思わぬ時間がとられる。両替不可もある。サービス不足は全国一だろう。
観光客にはまことに不親切。標識のない交差点では何万台のレンタカーが別の道に迷いこみ、時間を無駄にさせられていることか。 昔、ロシアをはじめとするワルシャワ条約軍の戦車がチェコスロバキアに侵入した。「プラハの春」は抑圧された。その時、チェコ市民は標識を塗りつぶし、ソ連の戦車の侵攻を少しでも遅らせようとした。立派な抵抗運動だ。
しかしレンタカーは侵略軍ではない。カネを落としてくれる観光客を迷わせてどうする。ウチナーンチュたちは「わが世の春」でヤマトンチュたちに抵抗しているのか。
観光客にはまことに不親切。標識のない交差点では何万台のレンタカーが別の道に迷いこみ、時間を無駄にさせられていることか。 昔、ロシアをはじめとするワルシャワ条約軍の戦車がチェコスロバキアに侵入した。「プラハの春」は抑圧された。その時、チェコ市民は標識を塗りつぶし、ソ連の戦車の侵攻を少しでも遅らせようとした。立派な抵抗運動だ。
しかしレンタカーは侵略軍ではない。カネを落としてくれる観光客を迷わせてどうする。ウチナーンチュたちは「わが世の春」でヤマトンチュたちに抵抗しているのか。
Posted by おさむちゃん at
09:52
│Comments(0)
2008年01月30日
沖縄の交通法規―2 むちゃくちゃでっせ
中央分離帯の適当な場所に切れ目がない。―私の住んでいるマンションに入ろうとすると大回りを強いられる。完成前に陳情したが、計画は前から決まっているとのことで拒否された。
酒飲んで運転する人・全国一 ―知人が2回つかまり、何十万円か払った。運転代行はタクシーよりも安いことがあるのに。
運転免許失効率・全国一 ―いつまでに何をしなくてはいけない、という納期意識はゼロ。約束、信義などにも無感覚。
運転免許くらい自由に失効させろ?。
バスは素通り・タクシーは寄ってくる ―バスは時間を守らない。中南米から来た人はなつかしがる。ヤマトから来た人はいらだつ。タクシーは向こうから客を探している。荷物を持って歩いているとクラクションを何度も鳴らされる。止まって待っていることも。雨の日、わざわざ向こう側からUターンしてきたことも。乗るときにはこちらから合図するって。
酒飲んで運転する人・全国一 ―知人が2回つかまり、何十万円か払った。運転代行はタクシーよりも安いことがあるのに。
運転免許失効率・全国一 ―いつまでに何をしなくてはいけない、という納期意識はゼロ。約束、信義などにも無感覚。
運転免許くらい自由に失効させろ?。
バスは素通り・タクシーは寄ってくる ―バスは時間を守らない。中南米から来た人はなつかしがる。ヤマトから来た人はいらだつ。タクシーは向こうから客を探している。荷物を持って歩いているとクラクションを何度も鳴らされる。止まって待っていることも。雨の日、わざわざ向こう側からUターンしてきたことも。乗るときにはこちらから合図するって。
Posted by おさむちゃん at
19:33
│Comments(1)
2008年01月30日
沖縄の交通法規―2 むちゃくちゃでっせ
中央分離帯の適当な場所に切れ目がない。―私の住んでいるマンションに入ろうとすると大回りを強いられる。完成前に陳情したが、計画は前から決まっているとのことで拒否された。
酒飲んで運転する人・全国一 ―知人が2回つかまり、何十万円か払った。運転代行はタクシーよりも安いことがあるのに。
運転免許失効率・全国一 ―いつまでに何をしなくてはいけない、という納期意識はゼロ。約束、信義などにも無感覚。
運転免許くらい自由に失効させろ?。
バスは素通り・タクシーは寄ってくる ―バスは時間を守らない。中南米から来た人はなつかしがる。ヤマトから来た人はいらだつ。タクシーは向こうから客を探している。荷物を持って歩いているとクラクションを何度も鳴らされる。止まって待っていることも。雨の日、わざわざ向こう側からUターンしてきたことも。乗るときにはこちらから合図するって。
酒飲んで運転する人・全国一 ―知人が2回つかまり、何十万円か払った。運転代行はタクシーよりも安いことがあるのに。
運転免許失効率・全国一 ―いつまでに何をしなくてはいけない、という納期意識はゼロ。約束、信義などにも無感覚。
運転免許くらい自由に失効させろ?。
バスは素通り・タクシーは寄ってくる ―バスは時間を守らない。中南米から来た人はなつかしがる。ヤマトから来た人はいらだつ。タクシーは向こうから客を探している。荷物を持って歩いているとクラクションを何度も鳴らされる。止まって待っていることも。雨の日、わざわざ向こう側からUターンしてきたことも。乗るときにはこちらから合図するって。
Posted by おさむちゃん at
19:31
│Comments(0)
2008年01月29日
沖縄の交通法規ー1
houkiとキーボードに入れたらまず放棄が出てきた。私のパソコンは、書こうとする意図を先取りして打ち出す予知能力があるようだ。たしかに沖縄は交通ルール放棄の島ではないか、と考える。いくつか私の体験したケースを挙げてみよう。
交差点で方向指示器を出さずに曲がる。―とても多い。後ろの車は迷惑。横断中の人は急に車が突っ込んでくる印象を受ける。
直線道路で横からの車を入れてあげる。―自分がどんどん直進すれば、横からの車は途切れた時に流入可能のはず。がら空きの道路で前の車が急ブレーキを踏んだので、あわてたことがある。原因はこれ。渋滞ともなると割り込み優先かと錯覚するほど。
曲がるべき交差点に標識がない。 ―近所の人以外は必ず間違える。住宅街を抜け高速道路に行こうと思ってもルート不明。
交差点で方向指示器を出さずに曲がる。―とても多い。後ろの車は迷惑。横断中の人は急に車が突っ込んでくる印象を受ける。
直線道路で横からの車を入れてあげる。―自分がどんどん直進すれば、横からの車は途切れた時に流入可能のはず。がら空きの道路で前の車が急ブレーキを踏んだので、あわてたことがある。原因はこれ。渋滞ともなると割り込み優先かと錯覚するほど。
曲がるべき交差点に標識がない。 ―近所の人以外は必ず間違える。住宅街を抜け高速道路に行こうと思ってもルート不明。
Posted by おさむちゃん at
15:02
│Comments(0)
2008年01月28日
謝花昇―3
自然を大事にするのは、今から考えると当たり前のことだが、当時はそうではない。その上、地元の役人達は賄賂をもらって無断開墾を容認していた。謝花は不当な開墾願いをことごとく不許可にした。
奈良原が面白いはずがない。その年、首里の士族200人の開墾願いが謝花によって却下された。これを契機に、奈良原は謝花を開墾主任から解任する。
しかし謝花は砂糖審査委員長、民法施行取調委員、農工銀工設立準備委員などの重要な仕事をこなしてゆく。明治31年、農工銀行常務となる。特権階級の私有物にならないように工夫を重ねるが、役員選出の際、奈良原一派の激しい妨害工作に敗れ追放される。
この頃は参政権もなく県議会も存在しないため、「琉球王」奈良原のやりたい放題であった。
「奈良原を追放しなければ沖縄県民は救われない」と謝花は決意する。野に下り、上京し奈良原追放を内相・板垣退助に訴えた。板垣は更迭を約束するが、内閣瓦解で実現されなかった。その後、謝花は選挙権獲得運動のため奔走する。
新聞で奈良原の悪政を暴き、刺客に襲われたこともある。私財を投げ打って運動を続けたが、病を得、明治41年10月29日、43歳の若さで亡くなった。10月31日、東風平村の自宅にて葬儀。
この日、4月に退任していた奈良原が、台湾の帰途、那覇に寄り歓迎会に臨んでいる。
奈良原が面白いはずがない。その年、首里の士族200人の開墾願いが謝花によって却下された。これを契機に、奈良原は謝花を開墾主任から解任する。
しかし謝花は砂糖審査委員長、民法施行取調委員、農工銀工設立準備委員などの重要な仕事をこなしてゆく。明治31年、農工銀行常務となる。特権階級の私有物にならないように工夫を重ねるが、役員選出の際、奈良原一派の激しい妨害工作に敗れ追放される。
この頃は参政権もなく県議会も存在しないため、「琉球王」奈良原のやりたい放題であった。
「奈良原を追放しなければ沖縄県民は救われない」と謝花は決意する。野に下り、上京し奈良原追放を内相・板垣退助に訴えた。板垣は更迭を約束するが、内閣瓦解で実現されなかった。その後、謝花は選挙権獲得運動のため奔走する。
新聞で奈良原の悪政を暴き、刺客に襲われたこともある。私財を投げ打って運動を続けたが、病を得、明治41年10月29日、43歳の若さで亡くなった。10月31日、東風平村の自宅にて葬儀。
この日、4月に退任していた奈良原が、台湾の帰途、那覇に寄り歓迎会に臨んでいる。
Posted by おさむちゃん at
10:25
│Comments(0)
2008年01月27日
謝花昇―2
謝花は学習院、東京農林学校(後の東京大学農学部)に学び、沖縄初の農学士となる。明治24年、27歳にして帰郷。東風平の人々はムシロ旗を立てて港で歓迎した。
その後は、県の産業・農業興隆の基礎固めに活躍、特に砂糖や米の現物支給から金納制度への切り替えに献身した。
謝花が沖縄に戻った翌年、奈良原繁が県令として赴任、翌26年には大規模な開墾計画を打ち出す。各地の杣山(そまやま)を開発する。産業を興し、廃藩置県で職を失った貧困士族の救済も大きな目的であった。
謝花は開墾主任に任命される。27年、国頭地方の巡視を命じられた謝花は、乱伐と乱開発の現状を眼にする。
「樹木の成長は遅い、今のようなでたらめな伐採では、炭や薪、材木などは将来他から買わなければいけなくなる、畑は荒れ、港は土砂で埋まる。」と警告した。
林業の専門家である謝花にとって、風害や水害で農民が大打撃を受けるのは眼に見えていた。
その後は、県の産業・農業興隆の基礎固めに活躍、特に砂糖や米の現物支給から金納制度への切り替えに献身した。
謝花が沖縄に戻った翌年、奈良原繁が県令として赴任、翌26年には大規模な開墾計画を打ち出す。各地の杣山(そまやま)を開発する。産業を興し、廃藩置県で職を失った貧困士族の救済も大きな目的であった。
謝花は開墾主任に任命される。27年、国頭地方の巡視を命じられた謝花は、乱伐と乱開発の現状を眼にする。
「樹木の成長は遅い、今のようなでたらめな伐採では、炭や薪、材木などは将来他から買わなければいけなくなる、畑は荒れ、港は土砂で埋まる。」と警告した。
林業の専門家である謝花にとって、風害や水害で農民が大打撃を受けるのは眼に見えていた。
Posted by おさむちゃん at
11:25
│Comments(0)
2008年01月26日
謝花昇―1
八重瀬町(旧東風平‐こちんだ‐町)庁舎の庭に、一人の男の銅像が立っている。謝花昇。沖縄民権運動の父。明治15年、初の県費派遣留学生5人の一人として上京。
それがどれほどの出来事であることかは、船旅で18日、東京に到着後、明治天皇に拝謁していることでも分かる。カタカシラ(チョンマゲのような髪型)に着物姿の写真が残っている。
彼らは最後の琉球国王・尚泰の屋敷にも度々招かれた。尚泰は明治12年の琉球処分以来、東京住まいを強いられていた。琉球からの留学生に対して、なつかしさと期待で万感迫る思いだっただろう。
しかし、彼らは「文明開化」の波に押され、ある日カタカシラを落とした断髪頭で現われる。以来、尚泰は彼らを寄せつけなかった。
近代化に取り残された国王と、琉球の明日を担う青年達との交流は途絶えた。
それがどれほどの出来事であることかは、船旅で18日、東京に到着後、明治天皇に拝謁していることでも分かる。カタカシラ(チョンマゲのような髪型)に着物姿の写真が残っている。
彼らは最後の琉球国王・尚泰の屋敷にも度々招かれた。尚泰は明治12年の琉球処分以来、東京住まいを強いられていた。琉球からの留学生に対して、なつかしさと期待で万感迫る思いだっただろう。
しかし、彼らは「文明開化」の波に押され、ある日カタカシラを落とした断髪頭で現われる。以来、尚泰は彼らを寄せつけなかった。
近代化に取り残された国王と、琉球の明日を担う青年達との交流は途絶えた。
Posted by おさむちゃん at
17:12
│Comments(0)
2008年01月25日
賞味期限―4
さて離島では止むを得ないこともある。なかなか商品が回転しないから賞味期限などかまっていられない。それが原因で思わぬもうけものをしたことがあった。港の売店でおみやげにお菓子を買った。店のお姉さんが、これどうぞ、と同じくらいの値段の饅頭を渡してくれた。箱のラベルを見るとあと1週間で賞味期限切れ。いちいち返却するのも面倒だからお客に渡してしまえ、という考えだ。これは良かった。
ところで米軍基地には賞味期限がないのだろうか。年代もののワインじゃあるまいし、いくらなんでも破棄しないと食中毒をおこす。
ところで米軍基地には賞味期限がないのだろうか。年代もののワインじゃあるまいし、いくらなんでも破棄しないと食中毒をおこす。
Posted by おさむちゃん at
12:24
│Comments(0)
2008年01月25日
賞味期限―4
さて離島では止むを得ないこともある。なかなか商品が回転しないから賞味期限などかまっていられない。それが原因で思わぬもうけものをしたことがあった。港の売店でおみやげにお菓子を買った。店のお姉さんが、これどうぞ、と同じくらいの値段の饅頭を渡してくれた。箱のラベルを見るとあと1週間で賞味期限切れ。いちいち返却するのも面倒だからお客に渡してしまえ、という考えだ。これは良かった。
ところで米軍基地には賞味期限がないのだろうか。年代もののワインじゃあるまいし、いくらなんでも破棄しないと食中毒をおこす。
ところで米軍基地には賞味期限がないのだろうか。年代もののワインじゃあるまいし、いくらなんでも破棄しないと食中毒をおこす。
Posted by おさむちゃん at
12:24
│Comments(0)
2008年01月24日
賞味期限なし―3
沖縄では、もの不足時代の考えをひきずっているのだろうか。今も賞味期限という考えが浸透しているとは言えない。そんなことを気にしていたら、ノイローゼになる。
小さな店で豆腐をレジへ差し出すと、あ、それ古いからやめた方がよいですよ、と別のものを渡してくれた。
大きなスーパーで野菜を手に取ると、「こちらの方がいいですよ」と係が新しいものを持ってきたことがある。
何故、最新のものを並べておかないのだろう。
店の作戦としてこんなことが考えられる。
・・古いものだが、知らずに買ってゆく客はそのままにしておこう。知っている人には新しいものを売ってあげよう、と考えてスタート。しかし実際にお客がレジまで持ってきて顔を合わせると、やはり気が咎めて作戦変更し、新しいものに代えてあげる。
・・いやいやそんなことは考えていない。要するにズボラなだけではないか。
小さな店で豆腐をレジへ差し出すと、あ、それ古いからやめた方がよいですよ、と別のものを渡してくれた。
大きなスーパーで野菜を手に取ると、「こちらの方がいいですよ」と係が新しいものを持ってきたことがある。
何故、最新のものを並べておかないのだろう。
店の作戦としてこんなことが考えられる。
・・古いものだが、知らずに買ってゆく客はそのままにしておこう。知っている人には新しいものを売ってあげよう、と考えてスタート。しかし実際にお客がレジまで持ってきて顔を合わせると、やはり気が咎めて作戦変更し、新しいものに代えてあげる。
・・いやいやそんなことは考えていない。要するにズボラなだけではないか。
Posted by おさむちゃん at
09:13
│Comments(0)